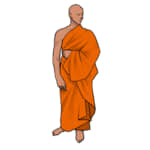日中戦争中に現地で撮影された戦争映画『土と兵隊』 国策映画の枠を超えたヒューマンドラマ【昭和の映画史】
■今も配信で観られる86年前の戦意高揚映画
今、映画『土と兵隊』を知っている人はどれぐらいいるだろう。何しろ昭和14年(1939年)の制作、86年前の映画なのだ。だが今はこの映画も配信で観られるようになった。
制作は日活多摩川撮影所で、監督は田坂具隆。世界三大映画祭で受賞した初の日本人監督である。昭和13年(1938年)、田坂が監督した『五人の斥候兵』が、ベネチア国際映画祭でイタリア民衆文化大臣賞を受賞した。
そして翌年、満を持して制作したのが『土と兵隊』である。時は日中戦争2年目、陸軍が制作に全面協力した国策映画で、実際に現地で撮影された。
昭和12年(1937年)7月7日に起きた盧溝橋事件は上海に飛び火、第二次上海事変につながった。中国軍の頑強な抵抗に遭った日本軍は、3個師団を杭州湾から上陸させることを決定する。物語はこの杭州湾上陸作戦から始まる。
ドキュメンタリーと見まがうばかりの作りだ。セリフは最低限で効果音などは一切なし。上陸した兵隊たちが進軍していく様子が淡々と描かれる。戦争映画であるにもかかわらず、映像がとても美しい。
モノクロならではの、白から黒までの色の濃淡が素晴らしい。中国の広大な大地に生えた背丈の高い草が風に揺れ、その間を粛々と進む様子は芸術的でさえある。兵隊たちは広大な中国大陸を、重い荷物を持って歩き続けた。その軍靴の響きが、通奏低音のように全編を貫いている。
敵と遭遇すれば戦闘になる。本物の銃器を用いているから、作り物ではない真実味がすごい。戦闘シーンと黙々と歩くシーンが延々と続き、その合間に小休止中のエピソードが挟まれている。
懐かしい故郷の歌を歌ったり、山羊の子を愛でたり、川の水を汲んで風呂を沸かしたりといった、極めて人間的な様子が描かれる。最小単位である分隊は、まるで家族のような絆で結ばれている。実際は分隊長の人柄によって内情は様々で、地獄のようだったという証言もある。
その分隊長は家族に手紙を書く。「自分たちは戦争で変わった。強くなった。成長したのだ」と。検閲官もそれを読みながら感銘を受ける。そして物語は最後、また歩き続ける兵隊の姿と軍靴の音で終わるのだ。
果たしてこれは戦意高揚映画と言えるのか。しかし映画評論家の四方田犬彦によれば、この辛さ苦しさの共有こそが戦意高揚の要だという。
「辛苦に耐えて自己犠牲を辞さない無名の日本人を描くことだけが、監督の主眼だったのであり、我々はこうした道徳主義を、日本のファシズムに特有の美学と見なすことができる」(『日本映画史100年』)
戦争は、兵隊が苦難に耐えて成長し、共同体への帰属意識を強めるための行為とされた。そして苦しみは美化され、「兵隊さんたちがあんなに苦労してるのだから、私たちも我慢しましょう」という[苦労のナショナリズム]が形成されたのである。
こういう感覚は、今も日本社会に潜在しているのではないだろうか。心を一つにして一緒に頑張ろうという日本人の美徳は、時として苦しみの共有を強いる。
とはいえ、監督の力量で『土と兵隊』は日中戦争の現実に迫り、86年前の映画とは思えない、国策映画の枠を超えたヒューマンドラマに仕上がった。最先端の技術を使えばいい作品になるわけではないようだ。
- 1
- 2